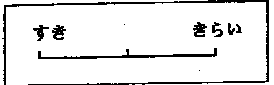
子供たちの意見は次の通りだった。
小学校/国語/3年生/物語/分析批評/手ぶくろを買いに/対役
東京都/村野 聡
3年生「手ぶくろを買いに」の第8(後半)・9・10時の授業。「対役(母さんぎつね)の変化」を検討する授業。
【第8時(後半)】
この物語は「主役の変化」が「対役の変化」を促す形になっている。母さんぎつねの、「ほんとうに人間っていいものかしら。」というつぶやきである。
これを授業で扱う。
母さんぎつねの気持ちは変化しましたか。しませんか。ノートに自分の考えをまとめなさい。
こう指示して、この時間はノートに自分の考えを書くことで終えた。
意見分布は次の通りだった。
変わった・・・・・18人 変わらない・・・・・10人
【第9時】
討論する。まずは、指名なし発表で全員が自分の立場を主張する。ネームプレートを黒板に貼り付け自分の立場を明らかにする。
人数の少ない「変わらない」派からの発表である。
主な主張は次の通りであった。
「P80で『本当に人間はいいものかしら。本当に人間はいいものかしら。』というのは、まだ納得していないと思う。だから変わっていない。」
続けて「変わった」派の発表である。
次のような主張が発表された。
「お母さんぎつねははじめP70で『人間って、ほんとにこわいものなんだよ』と言っているのに最後はP80で『本当に人間はいいものかしら。』とゆれている から変わった。」
「最後のお母さんぎつねは人間がこわいのかこわくないのかわからなくなっている。だから変化している。」
「『本当に人間はいいものかしら。』ということは少しは変化している。」
全員の発表が終わったところで反対意見を出し合った。
「前はお母さんぎつねは人間が大嫌いだったのだから、最後は少しは変化しているのではないですか。」
「『変わらない』はおかしいです。母さんぎつねは主役ではないけれど少し、変化しているんじゃないんですか。」
「『変化しない』に反対します。最初は人間はこわいものと言っていたけれど、子ぎつねの話を聞いて少しはこわくないと考えたんではないんですか。」
「どこにそう言葉で書いてあるんですか。」
「・・・・・・・・。」
「『本当に人間はいいものかしら。』というのはまだ納得していないと思います。」
「『本当に人間はいいものかしら。』という言葉の中に少しは人間をすきになったという気持ちも入っていると思います。少し好きになった気持ちをここで言っ ているのだから少しは変化しているんじゃないですか。」
「少し考えさせてください。」
「助けます。『本当に人間はいいものかしら。』は文章じゃあないんですか。
「『本当に人間はいいものかしら。』って書いてありますよね。こわかったら『本当に人間はいいものかしら。』っていわないんじゃないですか。」
「もし、人間がこわかったら『本当に人間はいいものかしら。』じゃなくて、『本当は人間はこわいものなんだよ。』と言い聞かせるんじゃないですか。」
(以下略)
途中、「変わらない」派から、
「少し変わったのは変わったことにならないのではないか。」
という意見が出された。
これについては教師が「少しでも変われば変わったこととして考えよう」と説明して進めさせた。
討論は「変化している」派優勢のまま1時間続いたが決着はつかず次時へ持ち越す。
【第10時】
討論の続きをした。「変わらない」派が次々に意見変更を始めた。
「私は『変わらない』かた『変わった』に変更します。わけは、P80の後ろから5行目に『「まあ!」とあきれました。』で終わっていないからです。『「まあ!」と あきれました。』で終わっていれば変わっていないけれど、『「まあ!」とあきれましたが、』だから変わると思いました。」
「〜さんの意見で『変わらない』かた『変わった』に変更します。」
「変わった」派はさらに攻撃する。
「ぜんぜん全く変わらないのならば『本当に人間はいいものかしら。』なんて言う必要はないんじゃないんですか。」
「ぼくは『変わった』と思います。なぜかというと気持ちが変わっていなければこの役はいらないんじゃないんですか。」
「最初完全にこわいと思っているけど、『本当に人間はいいものかしら。』という言葉の中で少しは変わっているんじゃないんですか。」
そして、討論開始から10分で全員が「変わった」派になり決着を見た。
最後に、
母さんぎつねの気持ちはどのあたりまで来ていると思いますか。
と発問し、次の図を示した。
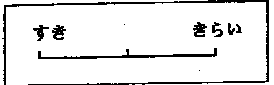
子供たちの意見は次の通りだった。
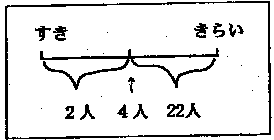
* 上の図は間違いである。「すき」「きらい」ではなく「こわい」「こわくない」にすべきであった。授業後の反省点である。