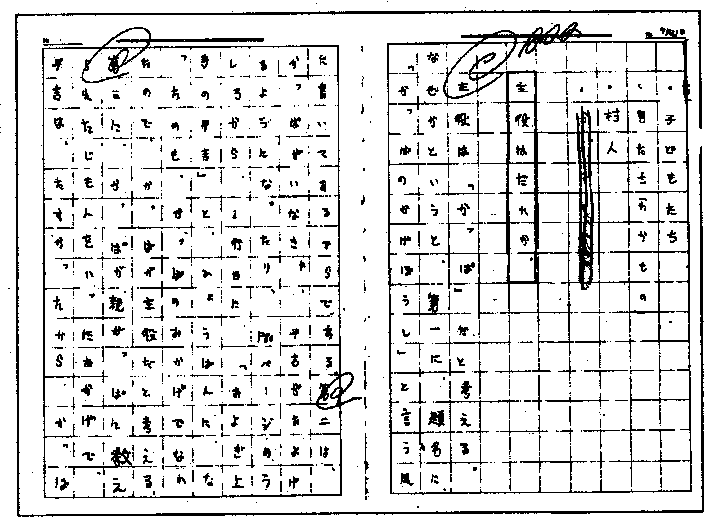
本論文は第7回「分析批評」上達講座(2000年3月19日)において向山洋一氏よりA評定をいただきました。 制作:東京都 村野 聡 TOSSランド
3年「かっぱのかげぼうし」(学校図書)
ミニ評論文の書かせ方
東京都東大和市立第二小学校 村野 聡
4 ポイント2ー「ノート指導」→「討論」→「ミニ評論文」の順序で書かせる
8 主役(平吉)は自分が泳げるようになったのは対役(かっぱ)のおかげだということを知っていたのかどうかの検討
向山学級、大森学級、伴学級のような長大な評論文に対して、比較的短い評論文を「ミニ評論文」と呼ぶことにする。時間的にも1時間の授業の中で十分に書ける程度のものとする。
ミニ評論文を書けるようにするためには、
|
ポイント1 4つの作文技術で書かせる ① 列挙 ② 主張 ③ 反論 ④ 引用 ポイント2 「ノート指導」→「討論」→「ミニ評論文」の順序で書かせる |
ことがポイントである。
4つの作文技術とは次の「定型」(アウトライン)のことである。
|
① 「列挙」の定型 第一に、~(一つ目は、~) 第二に、~(二つ目は、~) 第三に、~(三つ目は、~) |
|
② 「主張」の定型 ~は~か。<問いかけ> ~は~である。(~は~であると考える。)<結 論> なぜなら、~だからである。<根 拠> |
|
③ 「反論」の定型 ~は~か。 <問いかけ> ~は~ではない。(~はおかしい。)<結 論> なぜなら、~だからである。<根 拠> |
|
④ 「引用」の定型 教科書○ページ○行目に「 」と書いてあるので、~である。 |
「列挙」は自分の主張の根拠を複数説明したり、答えが複数あるときに、分かりやすく書くための作文技術である。
「主張」「反論」は自己主張するためには当然必要な作文技術である。
「引用」は根拠を不動のものにするために必要である。また、事実と意見、自己と他者の区別をはっきりさせる作文技術でもある。
この4つの作文技術の組み合わせで「評論文」が書けるのである。
4.ポイント2ー「ノート指導」→「討論」→「ミニ評論文」の順序で書かせる 目次へ
ミニ評論文を書かせる前に絶対に必要なステップがある。それは、
|
ノート指導 |
である。
どんなノート指導か。
|
ノートにぎっしり自分の意見を書けるようにする |
指導である。
ある発問に対する自分の意見をノートにできるだけたくさん書かせるのである。ノートに自分の考えを書かせる時も「定型」で書かせる。
ノート指導段階から「定型」で書かせ、ミニ評論文に必要な作文技術をトレーニングさせておくのである。
私は、ノート作業を個人でさせた後、同じ考えの者同士で意見交換させることにしている。(「作戦タイム」と呼ぶ)友達の意見も自分の意見としてどんどんノートに書かせる。
次に、こうして書けたノートをもとに、
|
討論の授業 |
をするのである。
子どもは「ノートに書いたことしか発表しない」のである。だから、「ノートにぎっしり」自分の考えを書かせるのである。どのくらいぎっしりかというと最低「見開き2ページ」は必要であろう。
討論は自分の考えが揺さぶられる場である。討論の授業で改めて考え直した自分の意見を、
| 「ミニ評論文」として書かせる |
のである。
3年生の物語教材に「かっぱのかげぼうし」(清水達也)がある。この教材を使って、ミニ評論文を書かせた実践例を紹介する。
単元の流れは次の通りであった。
|
1.音読 *2.登場人物の検討 *3.主役の検討 4.「できごと」の確認 5.主役の変化の検討 6.主役を変えたものの検討 *7.主役(平吉)は自分が泳げるようになったのは対役(かっぱ)のお かげだということを知っていたのかどうかの検討 (*は本レポートで提案している事例) |
「登場人物の検討」「主役の検討」「できごとの検討」「主役の変化の検討」など、何か一つ検討が終わるたびに原稿用紙にミニ評論文を書かせていった。
音読練習が終り、いよいよ内容に入っていく。
まず、次の発問をする。
| 登場人物はだれですか。ノートに箇条書きしなさい。 |
「登場人物」とは何か。その学習は1学期に終えている。すなわち、
|
物語に登場し、行動したり話したりする人やもの。物語を劇化するとして、その役が必要な場合、それは「登場人物」である。 |
3分たったところで、
「登場人物は今のところ何人いましたか。」
と、途中経過の確認をした。子ども達の意見には3人から8人の幅があった。
「登場人物は3人や4人ではなさそうだね。後1分考えなさい。」
と、もう1度考えさせた。
1分がたち、子どもたちの発表である。
|
・かっぱ ・平吉 ・千代 ・かげぼうし ・じい ・村人 ・子どもたち ・ばあ ・男たち ・女の子 ・親がっぱ |
「1つ1つ聞いて行きますので、登場人物ではないと思うものに手を挙げなさい。」
こう言って、1つずつ確認して行く。
子どもたちが多く反対したのが、「かげぼうし」「女の子」「親がっぱ」である。
「かげぼうし」は「平吉のかげ」だから違う。
「女の子」は「千代」のことだ。
「親がっぱ」は「かっぱの心の中に出るだけで、実際には登場していない。
こんな意見が出され、「登場人物」は確定した。
この授業で学んだことを「ミニ評論文」にさせる。
次の定型で書かせた。「列挙」である。
|
登場人物はだれか。 一人目は、「 」である。 二人目は、「 」である。 三人目は、「 」である。 |
さらに、授業で「登場人物」ではないとされたものについても、次の「反論」の定型で書かせた。
|
「 」は登場人物ではない。 なぜなら、~ |
この時、次のように話し、「引用」させるようにした。
「教科書の文を証拠にしなさい。」
「教科書○ページに何々と書いてあるからこうこうと言えるというとうに書き
なさい。」
黒板にも、
| 教科書P〇の前から〇行目に「 」と書いてあるので~である。 |
と書いておく。
子どものミニ評論文を紹介する。
|
登場人物はだれでしょうか。 一人目は、「かっぱ」です。 二人目は、「平きち」です。 三人目は、「千代(女の子)」です。 四人目は、「(千代の)ばあ」です。 五人目は、「男たち」です。 六人目は、「子どもたち」です。 七人目は、「村人」です。 八人目は、「じい」です。 「かげぼうし」は登場人物ではありません。 なぜなら、かげぼうしはかげで、きょうかしょの76ページ前から6ぎょう 目に、「なんだい。おらのかげぼうしか。」と書いてあります。 でも、その言葉は平きちがいってかげぼうしがゆっているわけじゃないか ら登場人物ではありません。 「親がっぱ」は登場人物ではありません。 なぜなら、親がっぱは、きょうかしょの85ページのまえから6ぎょう目に は、かっぱが親がっぱっていってたから親がっぱは、登場人物ではありませ ん。 (E.E) |
このように、「登場人物の検討」「主役の検討」「できごとの検討」「主役の変化の検討」など、何か一つ検討が終わるたびに原稿用紙にミニ評論文を書かせていく。ミニ評論文が集まって、少し規模の大きな評論文になっていく。トータルとして立派な評論文になっていく。子どもたちは、だんだん枚数を重ねていく原稿用紙が楽しみになる。
登場人物が確定したあとは、「主役」を検討させる。
| 主役はだれですか。 |
子どもたちの意見は「平吉」と「かっぱ」に分かれた。さっそく自分の意見をノートに書かせた。
次の、「主張の定型」と「列挙の定型」の組み合わせで書かせた。
|
主役はだれか。 主役は~と考える。 第一に、~ 第二に、~ |
この定型を板書し、
「~のところを自分で考えて書きなさい。」
と言って書かせる。
さらに、
「理由はなるべく教科書の文章を証拠にしなさい。このように証拠が書けるといいです。」
と言って、「引用の定型」を黒板に示す。
| 教科書○ページ○行目に「 」と書いてあるので、~である。 |
子どもたちは書き始める。
「第一の理由まで書けた子はノートを持っておいで。」
と、所々で個別にノートを見ていく。
「なるほど!」
「よく考えたね!」
短くほめて、自信を持たせる。。
「主張の定型」で書き終えた子には、「反論の定型」で反対意見を書き加えさせる。
|
~はおかしい。 なぜなら、~ |
ノート作業の時間はたっぷり取る。一時間は書かせる。ただし、途中で必ず、同じ意見の仲間で集まって情報交換させる。友達の意見も書かせる。子どものノートの一部を示しておく。
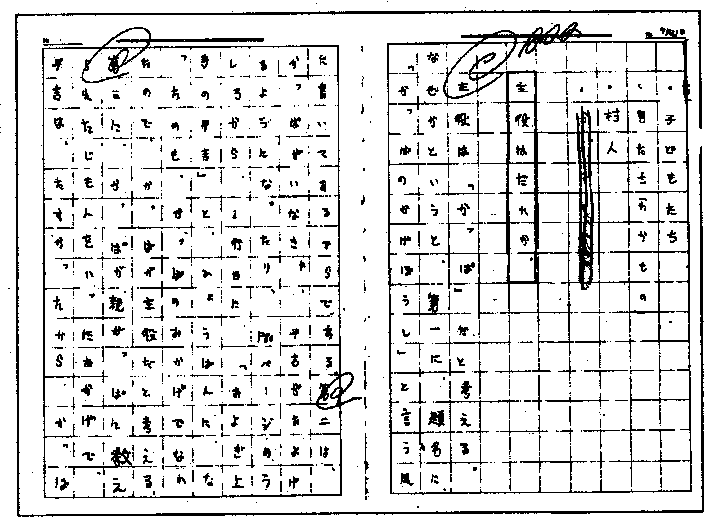
次の時間、ノートをもとに自分の主張を「指名なし発表」させる。
お互いの意見が分かったところで「指名なし討論」へと移った。
「平吉」派の主な主張点は次の通りであった。
・平吉は物語の始めから最後まで登場している。
・平吉には主役特有の「変化」が起きている。
・平吉が一番セリフが多い。
「かっぱ」派の主な主張点は次の通りであった。
・物語の題名に「かっぱ」とある。
・かっぱが平吉を何度も助けている。
結局、二時間討論した結果、全員が「平吉」派となって決着を見た。
ミニ評論文の書かせ方はノート指導する時と基本的に同じである。4つの作文技術で書かせる。ただし、討論を通しているので、次のように言って書かせる。
|
学習作文を書きます。自分のノートを中心に、話し合って分かったことも入れながら書きなさい。 |
三年生の子どもたちには「評論文」という言葉では教えていない。「学習作文」と教えている。
子どもたちが作文を書いている途中、教師は、
「すごい!れい君は証拠を○個も書いている。」
「おっ!るりちゃんは一年生が読んでも分かるように細かく、ていねいに、し
つこく書いている。」
などと言う。また、引用が正確にできている子の作文を全員に紹介したりする。
一人の成果を全体に広げているのである。
こうして、一人一人のミニ評論文の質を高めていく。
以上の指導により子どもに書かせた「ミニ評論文」
を紹介する。
|
主役はだれか。 主役は平吉だと考える。 第一に、P76の「かっぱのかげぼうし」の左どなりに、「川に流れた千代を助けようと、 平吉はとびこんだ。とびこむとすぐ、流れにのまれた。」とかいてある。これは、平吉の事なので 平吉が主役だと考える。 第二にP79には、ぜんぜん泳ぐゆう気がなかった平吉だった。だけど、P 84には、千代がおぼれているのを見て、すぐに、水にとびこんだ。だから、 さいしょは泳ぐゆう気がなかった平吉→さいご、泳ぐゆう気がでた平吉。と、 言うようにへんかしているから主役が平吉だと考える。 かっぱは主役ではない。なぜなら、かっぱだけが出ているページといえば、 P82だけだし、かっぱは、さいしょとさいごがかわっていないから、かっぱ は主役じゃないと考える。 かっぱは主役ではない。なぜなら、いくらだい名に、「かっぱのかげぼうし」 とかいてあったって、だい名にあるからだとはかぎらない。「つりばしわた れ」のトッコのときだって、主役はつりばしじゃなくて、トッコだったから だ。だから、かっぱは主役ではないと考える。 (A.H) |
8.主役(平吉)は自分が泳げるようになったのは対役(かっぱ)のおかげだということを知っていたのかどうかの検討
「できごと(エピソード)の確認」「主役の変化」「主役を変えたもの」について学習後、次のメイン発問をした。(「できごと」「主役の変化」「変えたもの」のミニ評論文については児童の作文例を参照のこと。)
| 平吉は自分が泳げるようになったのはかっぱのおかげだということを知っていたのか。 |
意見は3つに分かれた。
① 最初から最後まで気づいていない
② 最初から気づいている
③ 途中から気づいている。
討論は①か③に絞られた。
子供のミニ評論文を示す。子供たちは「定型」をかなり使いこなす。
|
平吉は自分が泳げるようになったのはかっぱのおかげだと知っているのか。 わたしは気づいていないと考えます。 第一に平吉はかっぱの事にきづいている所は教科書にはかいていないから です。 第二に平吉がかっぱに気がついた所は絵とかできごとになるのにのってい ないからです。 第三に84ページのうしろから2ぎょうめに「助けてくれー。」と平吉がさ けんだけどかっぱがたすけたとしっていたら「かっぱよ助けてくれー。」とさ けぶはずだからです。 第四にP86の後ろから5ぎょうめに「あれれこれは。」とかいてあります。 その次にかっぱが平吉の事を助けた事を知っていたら「かっぱよしぬな。」と かいうはずなのにいわないからです。 第五にP84の後ろから6ぎょうめに「平吉はむちゅうで川にとびこんだ。」 と言う所にしょうこがあります。「むちゅうでとびこんだ。」ということは自 分がおよげると思っていると思います。もし、泳げない事を知っていたら「お らは本とうはおよげない。だれか、助けてくれー。」と言うはずなのにいわな いからです。 (K.N) |
私の指導不足でなかなか「授業内容」を上回るような「学習内容」の書かれた評論文を実現できないでいる。
子供に申し訳がない。
それでも、今回の指導で「初めて、原稿用紙十枚も作文が書けた!」と、喜び、作文に自信をつける子も生まれた。
一度、このような経験をした子の作文は急速によくなっていく。
そういった子供の変容が少しでもあったことは嬉しいことであった。
ミニ評論文は子どもを変えるのである。 目次へ